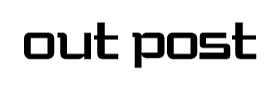年収1200万円は高所得?手取りや税金の割合に変化はあるか

年収1200万円となると一般的にみると高収入、富裕層と思われるところです。
しかし、収入が増えると税金も増えます。
実際の手取りや税金の割合の変化がどうなっているのかを見ていきます。
また、手取りを増やす節税方法を合わせて紹介します。
Contents
年収1200万円は高所得なのか

給与所得者で年収1200万円近く稼げる職業は限られてきます。
年収の平均は全体で約360万円という調査結果もあることから、やはり年収1200万円は高所得の部類に入るといえるでしょう。
それでは、年収1200万円の世帯の割合や、どのような職業があるのかなどを詳しく見ていきましょう。
割合
年収1200万円の場合、給与所得控除を差し引くとおよそ930万円になります。
実際は、さらに社会保険料控除などを引けるので、所得はもっと少なくなります。
厚生労働省が所得金階級別に世帯数をまとめたデータによると、所得が800万円から900万円だと全体の4.7%であり、900万円から1000万円だと全体の3.9%となっています。
このことから、年収1200万円の世帯は全体の4%前後だといえるでしょう。
割合からみても、それほど多くはいないことが分かります。
しかし、1000人いたら約40人いると考えると、そこまで限られた人ともいえないかもしれません。
職業
では、どのような職業の人が年収1200万円ほど稼いでいるのでしょうか。
高収入のランキングを見ていると、やはり大手企業の名前が並んできます。
その中でも、証券会社やテレビなどのマスコミ業界、大手商社、金融、不動産会社などの名前が年収1200万円前後に見られます。
また、一般的に高収入といわれる職業には医者や弁護士、パイロット、大学教授などがあります。
給与所得者のほか、自営業者や投資家なども年収1200万円となることがあるでしょう。
会社務めと違って収入が不確かなので、実際に年収がいくらになるかはその人の実力次第といえます。
サラリーマンが副業として投資を行うこともあり、給与所得と合わせて年収1200万円ということもあるようです。
不動産投資はうまくいけば安定した家賃収入を得ることが可能です。
一般的な職業のほか、スポーツ選手や芸能人なども年収1200万円以上となることがあります。
人気や実力で収入が変わるため、一概にいうことはできません。
年収1200万円の手取り額とは

年収1200万円があっても、実際に使える額は1200万円とはなりません。
収入に対して所得税や住民税などの税金が引かれますし、社会保険料の支払いもあります。
そういったものを差し引いて、実際に手元に入るお金を手取り額といいます。
年収1200万円ある場合、手取り額はどれくらいになるのか考えていきましょう。
手取りの額の定義
手取りと年収は混同されがちです。
会社に勤めている場合、給与の総額から社会保険料や税金があらかじめ天引きされて支払われます。
こうして支払われた金額が手取りです。
手元に入ったお金を年収と思う人もいるようですが、それだと実際の年収よりも低い金額になってしまいます。
また、あらかじめ税金を天引きすることを源泉徴収といいます。
自営業者の場合は、同じ年収でも手取りが低くなるのが一般的です。
会社に勤めていると会社が負担してくれる社会保険料がありますが、自営業者の場合はすべて自分で負担することになります。
退職金やボーナスなどもありませんし、計算していくと同じ年収でも自営業者は手取りが低くなってしまうのです。
年収1200万円の手取り額
実際に年収1200万円の場合の手取り額を考えてみましょう。
まず、手取りを計算するためには、給与から社会保険料控除や基礎控除、給与所得控除などを引いて計算する必要があります。
課税対象となるのは年収ではなく、それらの所得控除を引いた金額になるからです。
ただし、これら控除される金額は個人差があり一概にいうことはできません。
ここでは給与所得者を想定し、基礎控除と給与所得控除を差し引いて税金を計算してみましょう。
給与所得控除額は年収によって段階的に計算されますが、上限が定められています。
平成28年分は年収1200万円から上限額の230万円、平成29年分では年収1000万円から220万円に変更されています。
基礎控除額は一律で、所得税の場合は38万円です。
所得税の計算は所得金額で変わってきます。
所得が900万円から1800万円以下までは税率33%です。
900万円までは23%なので、10%税率が増えることになります。
所得税を平成29年分の給与所得控除額を元に計算すると、年収1200万円では157万2600円という計算になります。
税率をかけたあとに引かれる控除額もあり、所得が高いと控除額が増えます。
それでも、年収が上がるほど税金を納める割合は高くなります。
年収に100万円の差があったとしても、手取り額の差は100万円ではありません。
1200万円は税率の変わる境目ではありませんが、税率は33%と所得税で取られる金額は高くなります。
住民税の場合は、所得に関係なく一律10%の所得割と、5000円の均等割りが課せられるのが基本です。
基礎控除額が住民税では33万円なので、年収1200万円では住民税が95万2000円という計算になります。
低所得の場合、税率が一律10%の住民税のほうが高くなってしまいますが、税率の割合が高くなる年収1200万円の場合は所得税のほうが高くなります。
ここで求めた額は、基礎控除額と給与所得控除額しか差し引いていないため、実際の税金はこれよりも少なくなるでしょう。
ちなみに、所得金に対して引くことができる所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、障碍者控除、扶養控除、配偶者控除などさまざまなものがあります。
子どもがいる夫婦の世帯では、扶養控除や配偶者控除などが影響してきます。
手取りを増やす節税方法とは

年収1200万円があっても、税金が引かれると手取り額は意外と多くありません。
税金を抑えることができれば、同じ年収でもしっかりと手取りを増やすことが可能です。
ヤフー知恵袋を見ても節税に関する質問が多く、気になったものは知恵コレにいれていきましょう。
ここでは3つの節税対策をご紹介します。
確定拠出年金
節税方法の一つとして確定拠出年金制度の利用があります。
年金というと国民年金や厚生年金などが一般的です。
この二つは、公的年金と呼ばれる日本年金機構が管理するもので、加入が義務付けられているものです。
それに対して、確定拠出年金は私的年金とよばれるものです。
公的年金と違って、自分の口座にいれた掛け金を自分自身で運用し積み立て、60歳以降に年金や一時金として受け取ることができる制度です。
運用次第では、将来受け取れる年金額が増えるので老後の蓄えとして活用できます。
運用益が非課税というのも嬉しいところです。
さらに、年金を受け取る際に公的年金額に合算して公的年金控除が受けられます。
一時金として受け取る場合にも、退職所得控除を受けられます。
老後の節税に繋がるだけでなく、確定拠出年金に拠出する掛け金は非課税です。
10万円を掛け金として拠出した場合、その10万円は所得控除に含まれます。
同じ金額を貯金するよりも所得控除を受けられる分、節税対策として有効です。
個人年金保険
個人年金保険も節税対策として有効な手段です。
保険といっていますが、実際には一定の年齢から年金のようにお金を受け取れる貯蓄型保険です。
個人年金保険として支払った保険料の一部を、所得から控除することができます。
保険なので、毎月一定額を引かれてしまうのはデメリットともいえますが、毎月一定額を貯金するのと同じという考え方もできます。
同じ金額を現金として残すより、所得控除できるので節税に繋がります。
ただし、個人年金保険でどれくらい将来的にお金が戻ってくるかは、その時の金利によって左右されます。
個人年金保険に加入する前に、金利や控除額から損得計算をしてみることをおすすめします。
ふるさと納税
ニュースなどでも目にすることがある、ふるさと納税も節税対策になります。
自分の好きな自治体に税金を納める制度と勘違いされることもありますが、ふるさと納税は自分が好きな自治体に寄付をして地域を応援しようという制度です。
寄付金の金額に応じて、地方の特産品などのお礼品がもらえます。
ふるさと納税で納めた金額を確定申告すると、寄付した金額分所得税から還付され、住民税の控除を受けることもできます。
また、確定申告が面倒だという場合、ワンストップ特例を利用するとより手軽です。
書類の手続きは必要になりますが、寄付先を1年間に5つまでにすると、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられるという制度です。
ふるさと納税は納めるだけ節税に繋がるかというと、適用額に決まりがあります。
まず最低2000円までは自己負担で、それ以上の金額を寄付する必要があります。
寄付に上限はありませんが、控除の限度額があるので効率良く節税を行う場合は限度額を計算する必要があります。
ふるさと納税サイトの簡単シミュレーションで、配偶者・扶養家族なしで計算すると、年収1200万では控除の限度額は22万8000円になります。
地域の特産品を手に入れられる上に節税対策になることから、ふるさと納税を行う人は近年増えています。
高収入だから考えなければいけない

年収1200万円は全世帯の割合からみても、高収入であることは間違いありません。
しかし、高収入なぶん多くの税金を支払っており、手元に入る金額とは大きな差があります。
また、人それぞれで税金の額や、控除されるものが違ってくるため、同じ年収でも所得には個人差があります。
いくら高収入だとしても、やはり手取り額はより多くしたいものです。
そのためには、複雑で移り変わる税金制度をよく理解し、節税対策をする必要があります。
将来のことを考え、長期的な展望を持ち、自分にあった節税をしていきましょう。
- 年収1200万円は確かに高収入だが、それだけ多くの税金も支払っている
- 「勝ち組」と呼ばれるような贅沢な暮らしをするには、節税対策なども必要になる
- 主な節税対策として、確定拠出年金、個人年金、ふるさと納税がある